DISCUSSION
Vol.4
倉方俊輔 建築史家
戦後の「ビル」から、これからの再開発を考える[後編]
2018/10/26

Q倉方さんが再評価する東京の戦後ビルを教えてください。
A : 例えば「SHIBUYA 109」(1978年、平面計画:駒田知彦、外装デザイン:竹山実)。商業建築でパッと形が思い浮かぶものは少ないと思いますが、これは例外で、誰もがあのシリンダー形状をイメージできるでしょう。アイコニックなだけでなく、渋谷の坂の地形を利用してテラスをつくるなど、地面に対する人の振る舞いも繊細に考えられています。
「帝国劇場」(帝劇ビル・国際ビル、1966年、設計:谷口吉郎・三菱地所)も、もっと評価したい。同じ日比谷にある村野藤吾設計の「日生劇場」(日本生命日比谷ビル、1963年)と比べ、あまり語られないのは、外観がただのビルのようだからかもしれません。でも、むしろそこに時代性が現れています。ビルの傑作です。断面を見ると劇場がビルの中に立体的に埋め込まれ、その隙間にオフィスがあったり、垂直動線があったりします。外装と劇場の内装を谷口吉郎が手がけていますが、劇場内部の壁面に有孔板のようなチープな工業製品を並べて吊るし、それらを光の効果で魅せるといったテクニックや、ロビー空間に猪熊弦一郎のステンドグラス、伊原通夫の彫刻を配し、アートと建築の大胆な融合が見られます。内観だけで劇場空間を成立させているのが、まさにモダンです。谷口吉郎は「ホテルオークラ東京」(1962年、現在建て替え工事中)のメインロビーなど、数多くの商業建築を手がけ、ファサードやインテリアのみという作品も少なくありません。それは独特の色気を出す意匠も巧みだった谷口の性格の反映ですが、公共建築が主流だった当時のジャーナリズムにおいては、そうした側面は見過ごされていたように思います。
ドコノモンの連載第1回で取り上げたのは、松田平田坂本設計事務所(現:松田平田設計)が設計した「ニュー新橋ビル」(1971年)です。テレビのニュースでよく見かける、サラリーマン街頭インタビューの背景でお馴染みのファサードです。プレキャストコンクリートのパネル数種を組み合わせて網目模様を構成し、モアレ的効果を生み出しています。設計担当者は1960年代に流行った錯視や視覚の原理を利用した抽象絵画「オプ・アート」にインスピレーションを得ています。夜になると、この網目模様の効果によってビルの中から漏れる光、外を取り巻く光が錯綜しているように見えます。低層部の商業フロアは玄関らしい玄関がなく、天井高は低く、回遊できるプラン。夜にも映える猥雑な雰囲気が、ここが戦後は闇市だったことを偲ばせます。しかし当時の主要な建築雑誌では発表されていません。地味な雑誌の中に、設計担当者の言葉を見出すことができました。
これら3つのビルは、現在も使われ続けています。当時のジャーナリズムの中心では語られてきませんでしたが、今後の都市的な設計に通じるヒントがあると感じます。参照すべきは、これまで有名とされてきた建築家の作品だけではありません。

SHIBUYA 109

帝国劇場
『東京モダン建築さんぽ』より(撮影:下村しのぶ)

ニュー新橋ビル
『東京モダン建築さんぽ』より(撮影:下村しのぶ)

帝国劇場・ロビー空間
『東京モダン建築さんぽ』より(撮影:下村しのぶ)

Q私たちは戦後のビルから何を学び、
今後の再開発に生かしていくべきなのでしょうか。
A : 雑誌『東京人』の2018年5月号で「東京ビル散歩」という特集が組まれました。再開発に肯定的とは言えない優れたスタンスをとってきた同誌が、初めて現在の再開発も取り上げた、画期的な特集だったと思います。私は「東京『ビル』考。」を寄稿しました。そこでは『東京建築ガイドマップ』以降、10年間考え続けていた戦後ビルに関する、現時点での考えをまとめました。
そもそも「ビル」とは何でしょうか。ビルは“Building”の和製略称ですが、日本で最初に「ビルディング(ビルヂング)」という言葉を広めるきっかけになったのは、明治時代、丸の内に建てられた「東京海上ビルヂング」(1918年、設計:曽禰中條建築事務所)でした。当時はビル=オフィスビルでした。今の「ビル」の元祖となったのは大正時代、同じく丸の内に建てられた「丸ノ内ビルヂング」(1923年、三菱合資会社地所部・桜井小太郎)です。オフィスビルでありながらも低層階に商業施設を複合させて大衆にも開放し、初めてオフィスワーカーだけでなく街の風景として「ビル」が捉えられるようになりました。「丸ビル」の愛称で親しまれ、1929年に大ヒットした歌謡曲「東京行進曲」の歌詞にも登場したほどです。1999年に解体され、現在の「丸の内ビルディング」(2002年、三菱地所設計)に建て替わりましたが、近代・戦後・現代に渡って使われ続けました。
これまでお話ししたことのまとめにもなりますが、「東京『ビル』考。」では、戦後ビルに学ぶべきだと考える、「ビル」ならではの性格を3つに要約しました。1つ目は「複合用途」。オフィスだけでなく、商業施設、劇場、駅舎など、戦前であれば別々に建ち、それぞれのスタイルをもっていたものを1つに集約したことは「ビル」の重要なポイントと言えるでしょう。2つ目は「シンプルなファサード」。「ビル」は複合性だけでなく、街の風景として捉えられるためにふさわしい外観が求められます。シンプルでわかりやすく、かつ威厳を備えたプロポーションであればこそ、「ビル」と認められるのです。3つ目は「公共性」。ビルは基本的に民間のもので、公共建築ではありません。しかし戦後ビルは内部が通り抜けられるようになっていたり、隣りのビルと軒高を揃えたり、私から「公共を担う」という強い意志が感じられます。
これら3つの性格は、有名な建築家の作品にも、そうではないビルにも共通しています。前者の代表を一つ挙げれば、新宿の「紀伊國屋ビルディング」(1964年、前川國男)です。書店だけでなく、下階に名店街、上階には演劇ホールなど複合的な用途を1つにまとめあげ、ファサード両脇の打ち込みタイルの外壁が揺るぎない存在感を示し、大通りと裏通りを結ぶ貫通通路を内包するなど、私からの公共性を一見すると目立たない箱型の中に詰め込んでいます。戦後ビルが追い求めた理想形の一つと言えます。
戦後ビルの格好よさは、「再開発」の格好よさではないでしょうか。ここに挙げた建築はどれも、現代と規模こそ違いますが、街をスッキリと整理整頓し、大衆に開く、「再開発」の名に値するものです。それまであった建築を壊し、新しい希望をつくるという気概を感じさせます。
建築においても、日本の過去の歴史に誇りを感じたり、そこから学んだりといったことが色々あろうかと思います。まず、江戸時代以前の、木造を中心としたものづくりや住まい方の伝統があるでしょう。次に、文明開化以降の近代化への努力とその達成も挙げられるかもしれません。これらは割に語られやすいものです。しかし、それだけではなく、戦後日本の建築から学ぶことも多いと見るのが私の立場です。戦後建築を、すでに乗り越えられた、現在からすれば未熟なものとだけ捉えるのではなく、冷静な歴史的な視点がそこに初めて注がれることで、まだ成長の余地のある理想を、現在にどうつなぐかという方策が見えてくるはずです。未来につながる建設行為は、そうした検討から生まれるに違いありません。
育まれてきた「ビル」の理念を、いかに未来化していくのか。私たちに必要なのは、真にわくわくさせる「再開発」だと考えます。

『東京人』
(都市出版 / 2018年5月号)
倉方俊輔/建築史家
PROFILE : くらかた・しゅんすけ/1971年東京都生まれ。建築史家。大阪市立大学准教授。早稲田大学大学院理工学研究科博士課程満期修了。日本近現代建築史の研究のほか、建築公開イベント「生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪」の実行委員や「東京建築アクセスポイント」理事を務めるなど、建築と社会を近づけるべく活動中。『東京モダン建築さんぽ』『東京レトロ建築さんぽ』(以上、エクスナレッジ)、共著『東京建築 みる・あるく・かたる』(京阪神エルマガジン社)、『ドコノモン』(日経BP社)、『吉阪隆正とル・コルビュジエ』(王国社)など著書多数。
ARCHIVE
-

Vol.1
建築 ― インダストリアル デザインからの視座[前編]
山田晃三/株式会社GKデザイン機構 取締役相談役 -
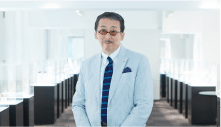
Vol.2
建築 ― インダストリアルデザインからの視座[後編]
山田晃三/株式会社GKデザイン機構 取締役相談役 -

Vol.3
戦後の「ビル」から、これからの再開発を考える[前編]
倉方俊輔/建築史家 -

Vol.4
戦後の「ビル」から、これからの再開発を考える[後編]
倉方俊輔/建築史家 -

Vol.5
未来のワンシーンを描く ー 1枚のスケッチの求心力[前編]
福田哲夫/インダストリアルデザイナー -

Vol.6
未来のワンシーンを描く ー 1枚のスケッチの求心力[後編]
福田哲夫/インダストリアルデザイナー -

Vol.7
環境建築・健康空間が経済を動かす ー ESG投資とウェルネスオフィス[前編]
田辺新一/早稲田大学創造理工学部建築学科教授 -

Vol.8
環境建築・健康空間が経済を動かす ー ESG投資とウェルネスオフィス[後編]
田辺新一/早稲田大学創造理工学部建築学科教授 -

Vol.9
イノベーションを起こすワークプレイス ― 環境が変われば、働き方が変わる[前編]
小堀哲夫/建築家 -

Vol.10
イノベーションを起こすワークプレイス ― 環境が変われば、働き方が変わる[中編]
小堀哲夫/建築家 -

Vol.11
イノベーションを起こすワークプレイス ― 環境が変われば、働き方が変わる[後編]
小堀哲夫/建築家 -

Vol.12
「社会のゆらぎ」をデザインする—— 広場的空間の研究vol.1[前編]
岡部祥司/株式会社スノーピークビジネスソリューションズ エヴァンジェリスト、NPO法人「ハマのトウダイ」共同代表 -

Vol.13
「社会のゆらぎ」をデザインする—— 広場的空間の研究vol.1[後編]
岡部祥司/株式会社スノーピークビジネスソリューションズ エヴァンジェリスト、NPO法人「ハマのトウダイ」共同代表 -

Vol.14
稼働率100%の公共空間のつくり方—— 広場的空間の研究vol.2[前編]
山下裕子/ひと・ネットワーククリエイター、広場ニスト -

Vol.15
稼働率100%の公共空間のつくり方—— 広場的空間の研究vol.2[後編]
山下裕子/ひと・ネットワーククリエイター、広場ニスト -

Vol.16
劇場空間の現在、そして未来—— 広場的空間の研究vol.3[前編]
伊東正示+丸山健史/株式会社シアターワークショップ -

Vol.17
劇場空間の現在、そして未来—— 広場的空間の研究vol.3[後編]
伊東正示+丸山健史/株式会社シアターワークショップ -

Vol.18
デザインの力で未来を切り拓く—— 若手アーティストの発掘[前編]
桐山登士樹/デザインディレクター -

Vol.19
デザインの力で未来を切り拓く—— 若手アーティストの発掘[中編]
桐山登士樹/デザインディレクター -

Vol.20
デザインの力で未来を切り拓く—— 若手アーティストの発掘[後編]
桐山登士樹/デザインディレクター -

Vol.21
映画で描かれる建築
—— 1960年代の特撮テレビと喜劇映画[前編]
磯達雄/建築ジャーナリスト -

Vol.22
映画で描かれる建築
—— 1960年代の特撮テレビと喜劇映画[後編]
磯達雄/建築ジャーナリスト -

Vol.23
「リノベーション」を通じて見る、これからのデザインプロセス[前編]
馬場正尊/建築家 -

Vol.24
「リノベーション」を通じて見る、これからのデザインプロセス[中編]
馬場正尊/建築家 -

Vol.25
「リノベーション」を通じて見る、これからのデザインプロセス[後編]
馬場正尊/建築家 -

Vol.26
イノベーションを起こすワークスタイル
――― 新しい時代の生き方vol.1[前編]
坂本崇博/合同会社SSIN代表、コクヨ株式会社働き方改革プロジェクトアドバイザー -

Vol.27
イノベーションを起こすワークスタイル
――― 新しい時代の生き方vol.1[後編]
坂本崇博/合同会社SSIN代表、コクヨ株式会社働き方改革プロジェクトアドバイザー -

Vol.28
ウェルネスとパフォーマンスマネジメント
――― 新しい時代の生き方vol.2[前編]
平井孝幸/株式会社ディー・エヌ・エー CHO室 室長代理、合同会社イブキ 代表 -

Vol.29
ウェルネスとパフォーマンスマネジメント
――― 新しい時代の生き方vol.2[後編]
平井孝幸/株式会社ディー・エヌ・エー CHO室 室長代理、合同会社イブキ 代表 -

Vol.30
大人を惹きつける「水塊」のつくり方
――― サンシャイン水族館「天空のオアシス」[前編]
中村元/水族館プロデューサー -

Vol.31
大人を惹きつける「水塊」のつくり方
――― サンシャイン水族館「天空のオアシス」[後編]
中村元/水族館プロデューサー -

Vol.32
大人を惹きつける「水塊」のつくり方
――― カスタマー起点の発想で、水族館を「メディア」化する
中村元/水族館プロデューサー -

Vol.33
Before-Before建築論
――― 歴史を紐解く設計術[前編]
鯵坂徹/鹿児島大学教授 -

Vol.34
Before-Before建築論
――― 歴史を紐解く設計術[後編]
鯵坂徹/鹿児島大学教授 -

Vol.35
地域プロジェクトを通して見えてくる
建築に求められる「+α」[前編]
竹内泰/株式会社あび清総合計画 代表取締役社長 -
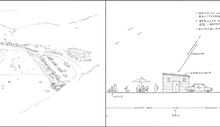
Vol.36
地域プロジェクトを通して見えてくる
建築に求められる「+α」[後編]
竹内泰/株式会社あび清総合計画 代表取締役社長 -

Vol.37
2050年、カーボンニュートラル実現に向けた日本の戦略[前編]
齋藤卓三/一般財団法人ベターリビング 住宅・建築センター評定・評価部長 -

Vol.38
2050年、カーボンニュートラル実現に向けた日本の戦略[後編]
齋藤卓三/一般財団法人ベターリビング 住宅・建築センター評定・評価部長 -

Vol.39
人びとを幸福にする、データを活用したまちづくり[前編]
一言太郎/ニューラルポケット株式会社 理事 -

Vol.40
人びとを幸福にする、データを活用したまちづくり[後編]
一言太郎/ニューラルポケット株式会社 理事 -

Vol.41
サインとは何か? サインデザインとは何か? [前編]
八島紀明/情報デザイナー -

Vol.42
サインとは何か? サインデザインとは何か? [中編]
八島紀明/情報デザイナー -

Vol.43
サインとは何か? サインデザインとは何か? [後編]
八島紀明/情報デザイナー -

Vol.44
火事に負けない木造建築物をつくる [前編]
安井昇/建築家、NPO法人team Timberize理事長 -

Vol.45
火事に負けない木造建築物をつくる [後編]
安井昇/建築家、NPO法人team Timberize理事長 -

Vol.46
Light is Life: 太陽の地球で人間と [前編]
東海林弘靖/照明デザイナー -

Vol.47
Light is Life: 太陽の地球で人間と [後編]
東海林弘靖/照明デザイナー -

Vol.48
世界は可能性に満ち溢れている―― プレイフルに知覚し、アクションを起こそう! [前編]
上田信行/同志社女子大学名誉教授、ネオミュージアム館長 -

Vol.49
世界は可能性に満ち溢れている―― プレイフルに知覚し、アクションを起こそう! [中編]
上田信行/同志社女子大学名誉教授、ネオミュージアム館長 -

Vol.50
世界は可能性に満ち溢れている―― プレイフルに知覚し、アクションを起こそう! [後編]
上田信行/同志社女子大学名誉教授、ネオミュージアム館長