DISCUSSION
Vol.3
倉方俊輔 建築史家
戦後の「ビル」から、これからの再開発を考える[前編]
2018/10/24

Q現在、東京都心部ではさまざまな再開発が進行しています。
建築史家の視点では、今の再開発ラッシュをどのように
見ていらっしゃるのでしょうか。
A : この東京駅周辺も大きく変わりつつありますね。そんな再開発の中、明治・大正期の建築が評価され、一部保存や復元などの取り組みも見られます。2016年にエクスナレッジから出版した自著『東京レトロ建築さんぽ』では、戦前の建築を「レトロ建築」と呼び、専門家向けではなく一般の方、どちらかというと女性向けに、「ディテールに物語性がある」「風合いがある」など、少しロマンチックな語り口で紹介しています。
その一方で、この周辺にも多く残る、戦後から1970年代に建てられ、築後50年を経過したビルは取り壊しが進んでいます。今まで語られてこなかったせいか、取り壊されることに社会も無関心で、あまり報道されません。実際、私も以前はそれほど気に留めていなかったのですが、約10年前に有楽町駅前の新東京ビルや国際ビルに出会って、その素晴らしさに衝撃を受けました。昨年出版した近著『東京モダン建築さんぽ』(エクスナレッジ、2017年)では、戦後から1970年代に建てられた建築を「モダン建築」と呼び、どう鑑賞したらいいのかを一般の方にも分かりやすく紹介しています。
「レトロ」という言葉は今や一般的ですが、それだけにこれまで建築史の世界で、ほとんど用いられていませんでした。「モダン」という言葉も同様です。ただ、これらはよく考えれば適切な用語であって、広く魅力を伝えていくためにも、これらは厳密に扱われるべきだと考えたのです。専門用語の解説から始めるのではなく、その以前の説明を尽くすべく、戦前のものを「レトロ建築」、戦後のものを「モダン建築」と呼んでいます。
明治・大正期、日本はヨーロッパの建築技術を取り入れると共に、そのデザインの仕方を導入しました。過去のふさわしい様式を参照するというやり方です。「レトロ建築」という用語がふさわしいのは、単に現在から見て古い建物というだけでなく、当時から過去を振り返り、かつて存在していたかのような一体感を生み出そうとした洋風建築だからです。
それに対して、戦後の「モダン建築」は、過去のスタイルから始めようとしないのが特徴です。それで無装飾で「見たことのない形」、民主的で「普段使い」しやすい建築を目指すようになります。例えば、戦前は劇場も学校もオフィスも、必ず玄関前には階段があり、人を上がらせて入れるという構えで格式の高さを表しましたが、戦後はフラットな構えで人が入りやすいような配慮が伺えます。民主的で機能的、身体性をもち、素材美を引き立てるデザインが「モダン建築」の特徴です。また、直接的な和風デザインが禁じ手となったことで、モダンのなかに日本情緒を漂わせる手法が花開き、前川國男や丹下健三など、国際的に通用する建築家も生まれます。彼らがリードした近代主義の建築を専門的には「モダニズム建築」と呼んでいますが、「モダン建築」は、より広義の言葉です。モダニズム建築は当時から評価され、多くの公共建築が採り入れましたが、それが戦後日本の建築の全てだったわけではありません。例えば、商業主義の建築は俗っぽいとされ、メディアで取り上げられることも少なかったのですが、よくみるとモダンの精神に溢れた建築もたくさん存在しています。無名を含めた「モダン建築」そのものを評価することで、初めて戦後の建築を、同時代のジャーナリズムの評価から独立した形で、歴史化できるのではないか。最近はそんな風に考えています。
こうした「モダン建築」は今でこそ参照する書籍がたくさんありますが、少し前までは乏しい状態でした。約10年前に出版した共著『東京建築ガイドマップ』(エクスナレッジ、2007年)では、新時代の東京の建築ガイドを生み出してみようと、明治・大正・戦前だけでなく、1970年代までの戦後建築も取り上げました。なぜ1970年代までだったかと言うと、1980年代以降の建築は、東京の現代建築を網羅した『建築MAP東京』(TOTO出版、2003年)で扱われている。戦前の建築については、藤森照信さん世代の蓄積がある。でも、その間のビルの時代がすっぽり抜けていたからです。もちろん、なかなか大変で、当時Googleのストリートビューがあれば良かったのですが、まだなかったので、昔の建築雑誌で目星をつけて実際に行ってみる、の繰り返し。すでに壊されてなくなっていた建築もたくさんありましたが、壊さずに使い続けられ、出会えた建築から学ぶことが多くありました。なぜ語られてこなかったのか、疑問に感じました。それが戦後のビルに着目することのきっかけにもなりました。
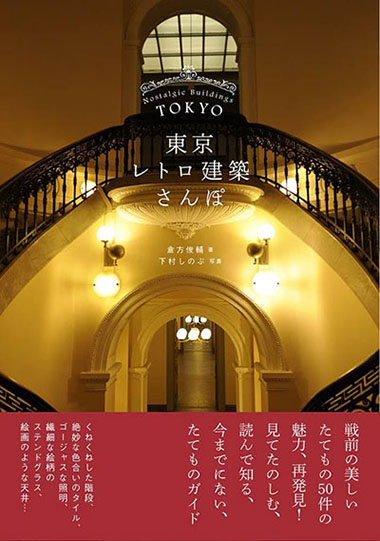
『東京レトロ建築さんぽ』
(エクスナレッジ / 2016年)

有楽町ビル『東京モダン建築さんぽ』より
(撮影:下村しのぶ)

新東京ビル『東京モダン建築さんぽ』より
(撮影:下村しのぶ)
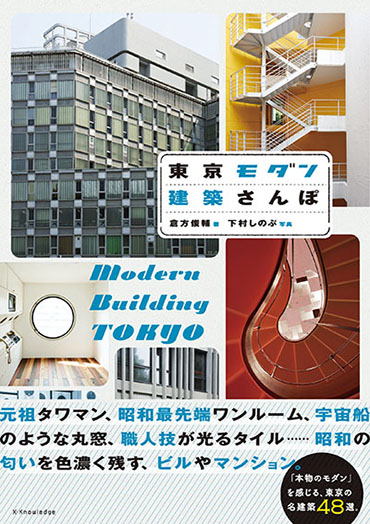
『東京モダン建築さんぽ』
(エクスナレッジ / 2017年)
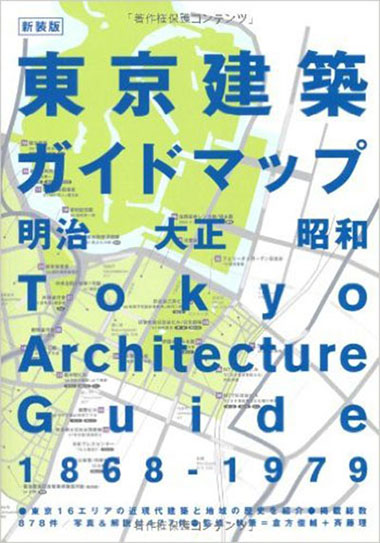
『東京建築ガイドマップ』(エクスナレッジ / 2007年)

Qこうした戦後の建築を保存するような取り組みは
行われているのでしょうか。
A : 1988年にオランダで設立されたDOCOMOMO(ドコモモ/Documentation and Conservation ofbuildings, sites and neighborhoods of the Modern Movement)は近代建築の記録と保存を目的とする国際的な運動を行っています。私も日本支部であるDOCOMOMO Japanに幹事として加わっています。まずこうした戦後の建築は、どこに何があるのかをリストにして、必要に応じて保存・改修を提案していくことが重要だと思います。
しかしDOCOMOMOも、丹下健三、前川國男、村野藤吾といったモダニズム建築家の作品や、建築学会賞を受賞した作品の登録が多いことから、有名建築家リストになっているのではないか、という疑問の声も聞きます。そうした背景から、DOCOMOMOの活動を補完するような形で、2008年に日経BP社のウェブサイト『ケンプラッツ』で始めた連載が『ドコノモン100選』です。DOCOMOMOをもじって、どこの誰がつくったかわからない、けれどいいものを「ドコノモン建築」と呼び、2011年に書籍化した『ドコノモン』(日経BP社)では23の建築を紹介しています。
私以外にも戦後のビルの再評価に取り組む人は増えてきています。もともとこうした活動は、私が2011年に大阪市立大学の教員となってから拠点としている関西の方が先行していて、魅力的な建築を一斉に無料公開する「生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪」を2013年から毎年開催しています。この活動を共に行っている高岡伸一さんは、以前から「BMC(ビルマニアカフェ)」というグループ名で大阪を拠点に無名のビルの魅力を発信し続けています。『いいビルの写真集』(パイインターナショナル、2012年)を出版したり、一般の目線で建築を楽しむようなイベントを仕掛けたりしています。古いビルでライブをやったり、かつてキャバレーだった場所で盆踊りをしたり。やはり「ビル」は使われることに意味があるのです。名古屋でも2011年に「名古屋渋ビル研究会」というユニットが結成され、活動を続けています。団地や土木、地形や暗渠など、普段の生活の隣にあるものの中に魅力を見出す動きが近年、静かに拡がっています。
戦後のビルもまたその一つとして、有名性を超えた、確かな価値を示しているように思います。

『ドコノモン』
(日経BP社 / 2011年)
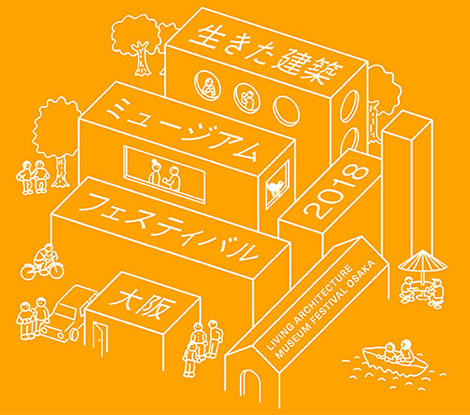
生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪 2018年 ホームページより
倉方俊輔/建築史家
PROFILE : くらかた・しゅんすけ/1971年東京都生まれ。建築史家。大阪市立大学准教授。早稲田大学大学院理工学研究科博士課程満期修了。日本近現代建築史の研究のほか、建築公開イベント「生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪」の実行委員や「東京建築アクセスポイント」理事を務めるなど、建築と社会を近づけるべく活動中。『東京モダン建築さんぽ』『東京レトロ建築さんぽ』(以上、エクスナレッジ)、共著『東京建築 みる・あるく・かたる』(京阪神エルマガジン社)、『ドコノモン』(日経BP社)、『吉阪隆正とル・コルビュジエ』(王国社)など著書多数。
ARCHIVE
-

Vol.1
建築 ― インダストリアル デザインからの視座[前編]
山田晃三/株式会社GKデザイン機構 取締役相談役 -
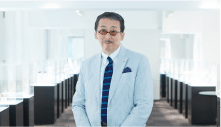
Vol.2
建築 ― インダストリアルデザインからの視座[後編]
山田晃三/株式会社GKデザイン機構 取締役相談役 -

Vol.3
戦後の「ビル」から、これからの再開発を考える[前編]
倉方俊輔/建築史家 -

Vol.4
戦後の「ビル」から、これからの再開発を考える[後編]
倉方俊輔/建築史家 -

Vol.5
未来のワンシーンを描く ー 1枚のスケッチの求心力[前編]
福田哲夫/インダストリアルデザイナー -

Vol.6
未来のワンシーンを描く ー 1枚のスケッチの求心力[後編]
福田哲夫/インダストリアルデザイナー -

Vol.7
環境建築・健康空間が経済を動かす ー ESG投資とウェルネスオフィス[前編]
田辺新一/早稲田大学創造理工学部建築学科教授 -

Vol.8
環境建築・健康空間が経済を動かす ー ESG投資とウェルネスオフィス[後編]
田辺新一/早稲田大学創造理工学部建築学科教授 -

Vol.9
イノベーションを起こすワークプレイス ― 環境が変われば、働き方が変わる[前編]
小堀哲夫/建築家 -

Vol.10
イノベーションを起こすワークプレイス ― 環境が変われば、働き方が変わる[中編]
小堀哲夫/建築家 -

Vol.11
イノベーションを起こすワークプレイス ― 環境が変われば、働き方が変わる[後編]
小堀哲夫/建築家 -

Vol.12
「社会のゆらぎ」をデザインする—— 広場的空間の研究vol.1[前編]
岡部祥司/株式会社スノーピークビジネスソリューションズ エヴァンジェリスト、NPO法人「ハマのトウダイ」共同代表 -

Vol.13
「社会のゆらぎ」をデザインする—— 広場的空間の研究vol.1[後編]
岡部祥司/株式会社スノーピークビジネスソリューションズ エヴァンジェリスト、NPO法人「ハマのトウダイ」共同代表 -

Vol.14
稼働率100%の公共空間のつくり方—— 広場的空間の研究vol.2[前編]
山下裕子/ひと・ネットワーククリエイター、広場ニスト -

Vol.15
稼働率100%の公共空間のつくり方—— 広場的空間の研究vol.2[後編]
山下裕子/ひと・ネットワーククリエイター、広場ニスト -

Vol.16
劇場空間の現在、そして未来—— 広場的空間の研究vol.3[前編]
伊東正示+丸山健史/株式会社シアターワークショップ -

Vol.17
劇場空間の現在、そして未来—— 広場的空間の研究vol.3[後編]
伊東正示+丸山健史/株式会社シアターワークショップ -

Vol.18
デザインの力で未来を切り拓く—— 若手アーティストの発掘[前編]
桐山登士樹/デザインディレクター -

Vol.19
デザインの力で未来を切り拓く—— 若手アーティストの発掘[中編]
桐山登士樹/デザインディレクター -

Vol.20
デザインの力で未来を切り拓く—— 若手アーティストの発掘[後編]
桐山登士樹/デザインディレクター -

Vol.21
映画で描かれる建築
—— 1960年代の特撮テレビと喜劇映画[前編]
磯達雄/建築ジャーナリスト -

Vol.22
映画で描かれる建築
—— 1960年代の特撮テレビと喜劇映画[後編]
磯達雄/建築ジャーナリスト -

Vol.23
「リノベーション」を通じて見る、これからのデザインプロセス[前編]
馬場正尊/建築家 -

Vol.24
「リノベーション」を通じて見る、これからのデザインプロセス[中編]
馬場正尊/建築家 -

Vol.25
「リノベーション」を通じて見る、これからのデザインプロセス[後編]
馬場正尊/建築家 -

Vol.26
イノベーションを起こすワークスタイル
――― 新しい時代の生き方vol.1[前編]
坂本崇博/合同会社SSIN代表、コクヨ株式会社働き方改革プロジェクトアドバイザー -

Vol.27
イノベーションを起こすワークスタイル
――― 新しい時代の生き方vol.1[後編]
坂本崇博/合同会社SSIN代表、コクヨ株式会社働き方改革プロジェクトアドバイザー -

Vol.28
ウェルネスとパフォーマンスマネジメント
――― 新しい時代の生き方vol.2[前編]
平井孝幸/株式会社ディー・エヌ・エー CHO室 室長代理、合同会社イブキ 代表 -

Vol.29
ウェルネスとパフォーマンスマネジメント
――― 新しい時代の生き方vol.2[後編]
平井孝幸/株式会社ディー・エヌ・エー CHO室 室長代理、合同会社イブキ 代表 -

Vol.30
大人を惹きつける「水塊」のつくり方
――― サンシャイン水族館「天空のオアシス」[前編]
中村元/水族館プロデューサー -

Vol.31
大人を惹きつける「水塊」のつくり方
――― サンシャイン水族館「天空のオアシス」[後編]
中村元/水族館プロデューサー -

Vol.32
大人を惹きつける「水塊」のつくり方
――― カスタマー起点の発想で、水族館を「メディア」化する
中村元/水族館プロデューサー -

Vol.33
Before-Before建築論
――― 歴史を紐解く設計術[前編]
鯵坂徹/鹿児島大学教授 -

Vol.34
Before-Before建築論
――― 歴史を紐解く設計術[後編]
鯵坂徹/鹿児島大学教授 -

Vol.35
地域プロジェクトを通して見えてくる
建築に求められる「+α」[前編]
竹内泰/株式会社あび清総合計画 代表取締役社長 -
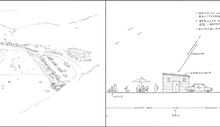
Vol.36
地域プロジェクトを通して見えてくる
建築に求められる「+α」[後編]
竹内泰/株式会社あび清総合計画 代表取締役社長 -

Vol.37
2050年、カーボンニュートラル実現に向けた日本の戦略[前編]
齋藤卓三/一般財団法人ベターリビング 住宅・建築センター評定・評価部長 -

Vol.38
2050年、カーボンニュートラル実現に向けた日本の戦略[後編]
齋藤卓三/一般財団法人ベターリビング 住宅・建築センター評定・評価部長 -

Vol.39
人びとを幸福にする、データを活用したまちづくり[前編]
一言太郎/ニューラルポケット株式会社 理事 -

Vol.40
人びとを幸福にする、データを活用したまちづくり[後編]
一言太郎/ニューラルポケット株式会社 理事 -

Vol.41
サインとは何か? サインデザインとは何か? [前編]
八島紀明/情報デザイナー -

Vol.42
サインとは何か? サインデザインとは何か? [中編]
八島紀明/情報デザイナー -

Vol.43
サインとは何か? サインデザインとは何か? [後編]
八島紀明/情報デザイナー -

Vol.44
火事に負けない木造建築物をつくる [前編]
安井昇/建築家、NPO法人team Timberize理事長 -

Vol.45
火事に負けない木造建築物をつくる [後編]
安井昇/建築家、NPO法人team Timberize理事長 -

Vol.46
Light is Life: 太陽の地球で人間と [前編]
東海林弘靖/照明デザイナー -

Vol.47
Light is Life: 太陽の地球で人間と [後編]
東海林弘靖/照明デザイナー -

Vol.48
世界は可能性に満ち溢れている―― プレイフルに知覚し、アクションを起こそう! [前編]
上田信行/同志社女子大学名誉教授、ネオミュージアム館長 -

Vol.49
世界は可能性に満ち溢れている―― プレイフルに知覚し、アクションを起こそう! [中編]
上田信行/同志社女子大学名誉教授、ネオミュージアム館長 -

Vol.50
世界は可能性に満ち溢れている―― プレイフルに知覚し、アクションを起こそう! [後編]
上田信行/同志社女子大学名誉教授、ネオミュージアム館長